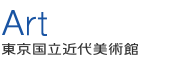生誕110周年
Denjiro Okochi and Daisuke Ito |
|
||||
| 2008.10.7-11.21 |
2008年10月7日(火)~11月21日(金)
※開映後の入場はできません
【料金】 一般500円/高校・大学生・シニア300円/小・中学生100円/障害者(付添者は原則1名まで)は無料
※無声映画プログラムは定員301名(各回入替制)、また弁士・
伴奏付き上映の入場料金は下記の通りです。
【料金】 一般1,000円/高校・大学生・シニア800円/
小・中学生600円/障害者(付添者は原則1名まで)は無料
【定員】 310名(各回入替制)
【発券】 2階受付
・観覧券は当日・当該回にのみ有効です。
・発券・開場は開映の30分前から行い、定員に達し次第締切となります。
・学生、シニア(65歳以上)、障害者の方は、証明できるものをご提示ください。
・発券は各回1名につき1枚のみです。
10-11月の休館日:月曜日、10月1日(水)-6日(月)
1920年に創立した松竹キネマ合名社で脚本家としてデビュー後、歌舞伎などの影響を受けた「旧劇映画」の伝統に映画独自の表現や話法を導入し、「時代劇映画」の確立に大きな役割を果たした巨匠監督・伊藤大輔(1898-1981)。
1925年に室町次郎の芸名で映画に初出演後、時代劇の全盛期を代表するスターとして活躍し、丹下左膳の当り役でも知られる大河内傳次郎(1898-1962)。
1926年に日活で運命的な出会いを果たした二人は、同年のコンビによる第一作『長恨』でたちまち日活の金看板となり、『忠次旅日記』(1927年)や『新版大岡政談』(1928年)など無声映画時代の日本映画を代表する傑作を次々と世に送りました。
不朽のコンビとうたわれた二人の生誕110周年を記念して開かれる本企画では、現存する日活時代のコンビ作品や初のトーキーによる左膳映画『丹下左膳 第1篇』(1933年)のほか、その後も時代劇の巨匠監督として、大スターとして、それぞれ揺るぎない足跡を残した二人の業績を、61作品(56プログラム)の上映を通して振り返ります。
また、10月21日から25日にかけての無声映画プログラムでは、一部の回で弁士、伴奏付き上映を行うほか、10月26日にはユネスコ「世界視聴覚遺産の日」を記念して、失われた幻の映画『新版大岡政談』を現存するスチル写真のスライド上映と弁士の説明、ピアノ伴奏で再構築する特別イベント「甦る『新版大岡政談』」を開催します。
皆様のご来場をお待ちしております。
【弁士紹介】
澤登翠(さわと・みどり)
故松田春翠門下。「伝統話芸・活弁」の継承者として“活弁”を現代のエンターテインメントへと甦らせ、「無声映画鑑賞会」「活弁in 学士会座」の定期公演、全国各地の映画祭への出演に加え、フランス、イタリア、ドイツ、アメリカなど海外でも多数の公演を行っている。日本映画ペンクラブ賞、文化庁芸術祭優秀賞他数々の賞を受賞。これまでに手がけた無声映画は500本を越える。昨年より失われた映画を現存する写真画像と音楽や語りで再構築する”ロスト・フィルム・プロジェクト”を始める。
【伴奏者紹介】(50音順)
鈴木真紀子(すずき・まきこ)/フルート
桐朋学園大学音楽学部卒。フルートを峰岸壮一氏に師事。1994年オーストリアとスイスで国際フルートセミナーに参加、ファイナルコンサートに出演。現在、楽団「カラード・モノトーン」や芹洋子のアコースティックバンドのメンバーとして活動。また、NHK放送博物館の室内楽シリーズにレギュラー出演中。
新垣隆(にいがき・たかし)/作曲・編曲、ピアノ
桐朋学園大学音楽学部作曲科卒。作曲を南聡、中川俊郎、三善晃の各氏に師事。楽団「カラード・モノトーン」のメンバーとして澤登翠とともに日本各地をまわる。自身の音楽作品としてはアンサンブル・ジェネシスのための「夏の庭」などがある。桐朋学園大学非常勤講師。
柳下美恵(やなした・みえ)/作曲・編曲、ピアノ
無声映画伴奏者。武蔵野音楽大学器楽科(ピアノ専攻)卒業。1995年、朝日新聞社主催の映画生誕100年記念上映会でデビュー以来、国内外の映画祭などで公演。昨年より、失われた映画をスチル写真などで再構築する“ロスト・フィルム・プロジェクト”を始める。紀伊國屋書店クリティカル・エディション・シリーズ『裁かるるジャンヌ』『魔女』の音楽を担当。2006年度日本映画ペンクラブ奨励賞受賞。
湯浅ジョウイチ(ゆあさ・じょういち)/作曲・編曲、ギター
1987年東京国際映画祭でD・W・グリフィスの『国民の創生』の音楽制作・演奏を行って以来、無声映画用の楽団版音楽の復刻と制作に尽力している。楽団「カラード・モノトーン」を結成し、澤登翠をはじめとする弁士とともに全国で公演。又、「ロックギタリストのためのJ・S・バッハ曲集」を出版している。ESPミュージカルアカデミー講師。