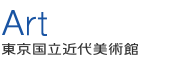2014年4月8日(火)~5月25日(日)
会場=大ホール
定員=310名(各回入替制)
料金=一般520円/高校・大学生・シニア310円/小・中学生100円/障害者(付添者は原則1名まで)、キャンパスメンバーズは無料
※消費税増税に伴い、2014年4月1日より入場料金が改定となります。
発券=2階受付
・観覧券は当日・当該回のみ有効です。
・発券・開場は開映の30分前から行い、定員に達し次第締切ります。
・学生、シニア(65歳以上)、障害者、キャンパスメンバーズの方は、証明できるものをご提示ください。
・発券は各回1名につき1枚のみです。
★開映後の入場はできません。
★4-5月の休館日:月曜日、3月31日(月)-4月7日(月)、5月26日(月)-29日(木)
映画に色彩を付ける試みは、その草創期から常になされてきました。無声映画期には、白黒映画フィルムへの彩色・染色・調色といった人工的な着色法が普及するとともに、現実の色を忠実に再現することを目指した「天然色映画」が試みられました。日本でも1914年から1917年にかけて、英国の《キネマカラー》方式の権利を獲得した天活が「天然色映画」を製作しました。
1930年代、三色分解撮影と捺染プリント方式を確立した《テクニカラー》が世界のカラー映画市場を席巻します。しかし大量のプリント作製を前提とする方式だったため、日本には根付きませんでした。その後、《コダクローム》や《アグファカラー》といった、より経済的な多層式カラーフィルムが登場し、これを受けて日本でも、戦中期に小西六写真工業と富士写真フイルムの2社が国産カラー映画の開発を進めます。
戦後、その試みは開花し、日本は《コニカラー》と《フジカラー》という2つの国産カラー映画方式を持つに至ります。しかし同時にこの時期は、内型ネガ・ポジ方式の《イーストマンカラー》をはじめとする、外国の新たなカラー映画方式が複数到来した、百花繚乱の時期でもありました。
本企画は、日本映画が本格的に色彩を獲得し始めた1950年代の作品(42プログラム・57本)を振り返り、映画における色彩表現の創造性と重要性を再発見する試みです。国内外のさまざまなカラー方式やカラーフィルム、また、巨匠たちのカラー映画への取り組み、さらには記録映画やアニメーションにおける色彩の探求などを観直すことにより、映画における色彩の役割をあらためて発見する機会になれば幸いです。
*上映プリントの中には、原版の経年劣化に伴う褪色やカラーバランスの崩れが見られるものが含まれています。
*作品区分は、(テクニカラーを除き)撮影に使用したフィルムの種類によるものです。
PDF版でもご覧いただけます →→ 「NFCカレンダー」2014年4-5月号