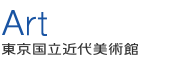2006年10月31日(火)~12月27日(水)
主催:東京国立近代美術館フィルムセンター
開映後の入場はできません。
定員=310名
発券=2階受付
料金=一般500円/高校・大学生・シニア300円/小・中学生100円/障害者(付添者は原則1名まで)は無料
・観覧券は当日・当該回にのみ有効です。
・発券・開場は開映の30分前から行い、定員に達し次第締切となります。
・学生、シニア(65歳以上)、障害者の方は、証明できるものをご提示ください。
・発券は各回1名につき1枚のみです。
2006年は、世界の映画史に輝く巨匠・溝口健二が逝去して50年となる記念の年です。鋭利で容赦ない人間への観察眼、妥協を許さぬ演出姿勢、そして大胆さと繊細さを兼ね備えたキャメラワークが生み出した溝口監督の傑作群は、日本国内だけでなく世界の映画人・映画ファンからの限りない敬愛を受けて現在に至っています。
1898(明治31)年、東京に生まれた溝口健二は、1920年に日活向島撮影所に入社、1923年に『愛に甦る日』で監督デビューを果たします。表現主義の洗礼を受けながら演出術を研鑽、やがて日活のトーキー第1作となる『ふるさと』(1930年)に携わります。名作『瀧の白糸』(1933年)などを生み出した無声映画時代を経て本格的なトーキー時代に入り、リアリズムの作風を身につけた溝口は、関西の風土に根ざした傑作悲劇『浪華悲歌』や『祇園の姉妹』(いずれも1936年)を発表、その後は『元禄忠臣蔵』(1941-42年)といった大作にも起用されるようになりました。
終戦後の溝口は、世情の移り変わりを踏まえながら新しい映画作りを模索、『夜の女たち』(1948年)からは従来のリアリズムを深化させ、さらに古典文学をベースにした『西鶴一代女』(1952年)や『雨月物語』(1953年)、さらに『山椒大夫』(1954年)といった畢生の傑作群を生み出すことで、フランスを始めとする海外でも高い評価を得るようになります。1956年の逝去は、あまりに早かったと言わざるを得ません。
また、溝口の映画世界を語るには、脚本家の依田義賢、撮影の宮川一夫、美術の水谷浩といった類い稀な才能を擁した協力者たちの名を欠かすことはできません。さらに“女性映画の名手”としての溝口にフォーカスを当てるならば、身勝手な男たちの中で翻弄される女性像を演じた山田五十鈴や田中絹代、京マチ子といった名女優たちもそこに加わるでしょう。
フィルムセンターはこの貴重な機会に、フィルムの現存する34の監督作と、溝口の人間性と創作の秘密を追ったドキュメンタリーを合わせた計35本を連続上映いたします。フィルムセンターでは、1978年6月に「溝口健二監督特集」を開催して以来28年ぶりの本格的な同監督特集となります。世界に冠たる溝口芸術の真髄に触れていただければ幸いです。
■(監)=監督 (原)=原作・原案 (脚)=脚本・脚色・潤色 (撮)=撮影 (美)=美術・装置・舞台設計 (音)=音楽・選曲・作詞 (出)=出演
■記載した上映分数は、当日のものと多少異なることがあります。
■本企画で上映する一部の無声映画作品は、小ホール上映企画「シネマの冒険 闇と音楽2006」で、11月3日(金・祝)から11月5日(日)に活弁もしくは音楽伴奏つきで上映されます。