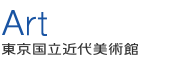(計83分)
(6分・16fps・35mm・無声・染色)
蓮如ゆかりの地・福井県吉崎に伝わる説話「肉付の面」の映画化。姑の嫁いびりの話で、姑が夜道で鬼の面をかぶって嫁を脅かそうとすると、面が顔に貼り付いて取れなくなってしまう。元素材の可燃性プリントのストックが1921年であることから、牧野教育映画の『肉付の面』(1922年)と推測される。
'22(牧野教育映画)
(15分・16fps・35mm・無声・染色・不完全)
信仰心の厚い「妙好人」として知られた大和の清九郎を主人公とする宗教映画で、全3巻中第一巻目が発見された。吉野から京都の本願寺まで毎日何度も薪を背負ってお参りをしたり、亡き父が残した借金を律儀に返済しようとする場面が現存。
'22(東本願寺映画班)(原)(脚)沼法量
(15分・18fps・35mm・無声・白黒・不完全)
社会教育団体・修養團の宣伝映画として製作された教育劇映画で、酒飲みで芸者遊びに明け暮れる夫に対して、必ず改心してくれると信じて献身的に尽くす貞淑な妻の美談。物語の後半は欠落しているが、マキノプロダクションで鍛えた金森万象の手堅い演出が確認できる。協立映画プロダクションは1931年に金森が設立した独立プロ。
'32(協立映画プロダクション)(監)金森万象(原)蓮沼門三(撮)松浦茂(出)金子新一、弊原礼子、本田繁美、小泉光子、兒島武彦、岡村義夫、市原義夫、守本專一、嵯峨京子、浦路輝子、澤田慶之助
(16分・18fps・35mm・無声・染色)
蓮如にまつわる宗教映画で、物語の前半は吉崎の坊舎が火災にあった際に、死を覚悟で火の中へ飛び込み親鸞の聖典「信の巻」を救った了顕の殉教話。後半は信心深い父の源右衛門が、親鸞の御真影をお寺から返してもらうために、息子の源兵衛の生首を差し出すという話。若干重複場面があるが、元素材の可燃性プリントの編集のまま上映する。この可燃性フィルムは1934年に検閲されているため公開年を34年としているが、映像のスタイルから撮影はそれ以前の可能性がある。
'34(本派本願寺)
(31分・35mm・白黒・不完全)
働かずに酒ばかり飲んでいる主人公が、大金を拾ったことから巻き起こる騒動を描くことによって、勤労のすばらしさを謳った喜劇仕立ての教育映画。振進キネマは1921年に監督の井上麗吉が設立した老舗の教育映画プロダクションで、1920年代末には東京の町屋に500坪の撮影所を所有していた。
'36(振進キネマ社)(監)(原)井上麗吉(撮)川島精二(美)世羅昌一路(出)曽我廼家一二三、木村光子、高波三郎、塩谷つとむ、高石明、保瀨薫、鈴石時子、東大寺一郎、恩田清、加藤あき子、村田三樹子
■(監)=監督・演出 (原)=原作・原案 (脚)=脚本・脚色 (構)=構成 (画)=作画 (撮)=撮影 (美)=美術・舞台設計 (音)=音楽 (出)=出演
■本特集には不完全なプリントが含まれています。
■記載した上映分数は、当日のものと多少異なることがあります。
■プログラムの上映順序はやむを得ず変更になる場合があります。